![]()
2016年度 11月例会・第3回通常総会
2016.11.19
2016年11月16日(水)りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館劇場にて一般社団法人新潟青年会議所11月例会『災害対応と経済発展の共存~国土強靭化に向けた新潟の取り組み~』が行われた。
講師に、京都大学教授であり内閣官房参与を務めている藤井聡氏をお招きし、国土強靭化政策について地方創生との関係性を交えながらご講演をいただきました。
講師の考え方において、防災減災と経済政策は一緒であり、防災減災は経済成長にとって無駄になるという考え方が蔓延しているということであった。
防災減災が経済政策となる理由は、以下3つの通り。
①もしパラレルワールドがあったと仮定した場合(同じ地域を違う方向で発展させた場合)
1.防災工事をしっかりと行った都市(代わりにインフラ整備が遅くなる)
2.インフラ整備を進めた都市(防災工事を後回しにする)
この二つの都市を比較した場合、ひとたび災害が起こるとその度に2は余分な費用が発生してしまう。1の都市は、被害が出るものの、復興までに大きく費用が掛からない。20年30年と長期的な視野に立ったときの経済成長の期待値は、1が大きく、防災工事は成長戦略そのものとなる。
②防災減災とニューディール政策
公共投資を行うことで、雇用を作った政策であり、国土強靭化のインフラ投資を行うことで、関連企業が潤うようなフロー効果※1が生まれる。
③新幹線
現在首都圏に集中している90兆円のGDPの50兆円分を地方に分散させることで、首都圏に大規模災害が起こった場合でも、被害を少なく収めることができる。
そのために新幹線を広く開通することで、経済圏の連携をより緊密にすることが重要である。また、新幹線がある地域とない地域とでは、工業において2倍、商業においては11倍の成長率の違いがある。
また、BCP※2の連携を企業間で取り、ネットワークを構築することにより、ソフト面におけるストック効果※3を発揮し、業務効率に繋がっている実例も紹介された。
※1 フロー効果 : 公共投資を行うことで生産活動を活発にし、原材料や労働力の需要の拡大や生産機会・雇用機会の創出等、経済活動を活性化させる短期的な効果
※2 BCP : 災害などリスクが発生したときに重要業務が中断しないこと。また、 万一事業活動が中断した場合でも、目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴うリスクを最低限にするために、平時から事業継続について戦略的に準備しておく計画。
※3 ストック効果 : 例えば、道路が整備され供用されることで、人流・物流の効率化、民間投資の誘発や観光交流、人口・雇用などを増加させ、長期にわたり経済を成長させる効果
続くパネルディスカッションでは、藤井氏に加え、BCPの専門家であり危機管理教育&演習センター理事長を務めていらっしゃる細坪信二氏と、新潟県副知事の寺田吉道氏をパネリストとして招き、「災害対応と新潟の経済発展を共存させるための方策」をテーマに、行政の考え、大企業の動き、中小企業でも取り組めることを踏まえて議論しました。
BCP計画によって、首都圏から地方に本社機能を移した外資系企業の具体例を挙げ、新潟においても企業誘致が行われ、本社機能を移した企業があるとのことであった。また、中小企業において、会社間連携を行った企業の片方に、災害が発生し被災してしまった場合、既存販路への納品が遅れてしまわないよう、もう片方の被災をしていない企業の協力によって、納品を行えるよう技術の交換が行われているとのことだ。
災害大国である日本においては、行政と中小企業が協力を行い、今後はこのような取り組みが推進されていくようだ。このようにして、経済を発展させる考えがあることを知ることができ、大変勉強になりました。
 |
 |
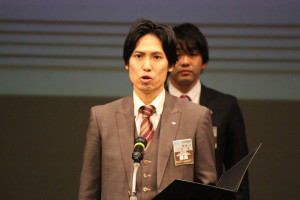 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
第3回通常総会
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
(取材・撮影・記事:河端・入山・後藤・塩谷・岩野)











